【地球の裏側を走る =アルゼンチンの車と人と街並み=】 No.14 第4部 ≪ブエノス・アイレス街巡り≫ 7. 家族全員でドライブ 日本の道路を走る車には運転者一人しか乗っていない車が多いが、アルゼンチンでは逆で、一人だけと言う車は、朝夕の通勤時間帯以外はとても少ない。というのは仕事以外は家族ぐるみで外出したり、楽しんだりするというのが習慣だからである。休日はもちろん、夜の街でも大抵は定員一杯の人が乗っているし、ときには犬もちょこんと座っている。この習慣は日本人駐在員家庭の間にも浸透していて、日本では家族と一緒に夕食をとるのは週一回だ、などという猛烈社員もここではすっかり軟化して、男同士で一杯飲んだり仕事の話をしたりするのは昼食時にして、夜の交際は夫婦同伴とか家族ぐるみという形をとることが多い。休日の過ごし方も同様で、ゴルフ・コンペなどの他は家族単位で行動するようになる。異国での生活を大過なく送るには、家族の精神的・肉体的健康の維持が不可欠である。そのためには大変よい習慣だ。しかし、日本で生活しているとこうはいかない。それは何故だろうかと考えた。 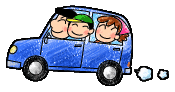 日本の場合、島国民族の日本人は昔は国外へ出られれなかったため、国民が皆知人、友人のような関係であった。従って人との出会いは、その時だけではなく、またきっと会う時があると信じられた。だからこそ、お金の貸し借りもできるし、世話になったらきちんとお返しをしておかないと、次ぎに会うときに恥じをかくと考えられてきた。これが義理と言うものであろう。要するに他人との交際が一過性ではなく、持ちつ持たれつといった継続性のある関係になるため、家族関係より他人同士の交際の方が大事だというように考えられてきた。反対に大陸民族や多種民族混合の社会では、一度出合った人、世話になった人でも、別れたらもう会うこともないだろうと考えられ、何事もその場限りで完結させてしまうという習慣ができた。このため、後日のお返しといったものもないし、義理も生まれない。食事などをご馳走しても後日礼を言われる事もないし、「夕べは主人がお世話になりました」なんて奥さんが礼をいうことなど全くない。従って、何かの場合においても他人の援助は期待できず、自分を支えてくれるのは常に肉親だけという哲学が生まれ、家族主義が発達してきたのだと思う。このような習慣の一端として、休日のドライブも家族全員プラス・ワン(犬)といった構図が出来、時には一台の車に6人も7人も詰め込んで、わいわいがやがやの道行きとなるのだ。地勢的条件を始め、戦争経験の有無とか建国以来の諸々の歴史に培われた民族性の産物である人間の習性は、どっちが良いとか悪いとかの問題ではなく、お互いに郷に入ったら郷に従えと言う柔軟性のある処世述を持つ事が、外国において楽しく暮らすための一つの条件だと思ったものである。 日本の場合、島国民族の日本人は昔は国外へ出られれなかったため、国民が皆知人、友人のような関係であった。従って人との出会いは、その時だけではなく、またきっと会う時があると信じられた。だからこそ、お金の貸し借りもできるし、世話になったらきちんとお返しをしておかないと、次ぎに会うときに恥じをかくと考えられてきた。これが義理と言うものであろう。要するに他人との交際が一過性ではなく、持ちつ持たれつといった継続性のある関係になるため、家族関係より他人同士の交際の方が大事だというように考えられてきた。反対に大陸民族や多種民族混合の社会では、一度出合った人、世話になった人でも、別れたらもう会うこともないだろうと考えられ、何事もその場限りで完結させてしまうという習慣ができた。このため、後日のお返しといったものもないし、義理も生まれない。食事などをご馳走しても後日礼を言われる事もないし、「夕べは主人がお世話になりました」なんて奥さんが礼をいうことなど全くない。従って、何かの場合においても他人の援助は期待できず、自分を支えてくれるのは常に肉親だけという哲学が生まれ、家族主義が発達してきたのだと思う。このような習慣の一端として、休日のドライブも家族全員プラス・ワン(犬)といった構図が出来、時には一台の車に6人も7人も詰め込んで、わいわいがやがやの道行きとなるのだ。地勢的条件を始め、戦争経験の有無とか建国以来の諸々の歴史に培われた民族性の産物である人間の習性は、どっちが良いとか悪いとかの問題ではなく、お互いに郷に入ったら郷に従えと言う柔軟性のある処世述を持つ事が、外国において楽しく暮らすための一つの条件だと思ったものである。 車の行き先は一般には「アサード(焼肉)」のできる林の中とか、サッカーのできるような場所であるが、中流階級になると「キンタ(別荘)」や、会員制スポーツクラブであるカントリー・クラブへ行く。そこでは、夫はゴルフ、妻や子供はテニス、乗馬、水泳など皆がそれぞれに楽しみ、いつもデパルタメントの室内で飼われている犬達は、新鮮な空気を胸一杯に吸ってゆっくり昼寝をするといったレクリエーションが繰り広げられる。 そう言えば、ブエノス・アイレスの街には犬の散歩屋がある。れっきとして職業往来に載っているのかどうか知らないが、毎日朝夕に何匹もの犬をまとめて引き連れ、散歩をさせる屈強な若者を見かける。市内のバリオ(住宅地)は殆どデパルタメントなので、犬は皆部屋の中で飼われている。しかし、散歩に連れて行きたくても、足の弱った老人にはとても犬の相手は無理なので、このような散歩屋なるものが必要になるのだと思う。 ≪写真:大勢の犬を引き連れて街中を歩く、「犬の散歩屋」。多いときには20匹以上も連れている若者もいる。≫ |